先日「本を買った」でまとめあげてしまった日記を
もっと細かく詳細に、かつその本についても書いてみようと思います。
はじめて手にした海外文学は何だったんだろう。
家にまだとってある「岩波世界児童文学集」が数冊あるから、
きっとドリトル先生とか、メアリー・ポピンズ、あるいは赤毛のアンとかだろうか(どれも名作!)。
でもここで言う(それこそ今回の本に載っているような)海外文学はズバリカラマーゾフの兄弟であり、ゴドーを待ちながらであり、
帯を書いている岸本佐知子さんが翻訳をしているような海外の著作を指す。
そういった意味で、
私はいつ海外文学に興味を持ち始めたのか今考えているけど、少なくとも大学時代は日本文学ばかり読んでいた。
だからきっと大学を出て、しばらく経ってからのような気がする。
思えば高校時代も、海外文学は国語の教科書に載っていなかった気がする。
国語、というくらいだから国の文学でないといけないのだろうか、分からないけど。
思春期に夏目漱石の『こころ』を読んでうら暗い気持ちになった記憶はあるが、海外文学を読んでうら暗い気持ちになった覚えがない。
英米、韓国、とまだかたよりがあるけど、
いろいろ読み始めてその地域によって文学の香りのようなものに違いがあることを知ったので
やはりその地域によって文学のもつ色合いに違いはあるから
掲載すればいい。
( 余談 )

じゃーーーーーん
今手にもっている『やりなおし世界文学』でピックアップされている?作品は以下だ。
- 『華麗なるギャツビー』スコット・フィツジェラルド
- 『ねじの回転』ヘンリー・ジェイムズ
- 『脂肪の塊・テリエ館』モーパッサン
- 『流れよわが涙、と警官は言った』フィリップ・K・ディック
- 『たのしい川べ』ケネス・グレーアム
- 『アシェンデン 英国秘密情報部員の手記』サマセット・モーム
- 『わらの女』カトリーヌ・アルレー
- 『パーカー・パイン登場』アガサ・クリスティー
- 『スポンサーから一言』フレドリック・ブラウン
- 『終りなき夜に生れつく』アガサ・クリスティー
- 『かもめ』アントン・チェーホフ
- 『ストーカー』A&B・ストルガツキー
- 『新編 悪魔の辞典』アンブローズ・ビアス
- 『ムッシュー・テスト』ポール・ヴァレリー
- 『闇の奥』コンラッド
- 『ノーサンガー・アビー』ジェイン・オースティン
- 『813』『続813』ルパン傑作集 モーリス・ルブラン
- 『クローム襲撃』ウィリアム・ギブスン
- 『長いお別れ』レイモンド・チャンドラー
- 『トニオ・クレーゲル ヴェニスに死す』トーマス・マン
- 『山月記・李陵 他九篇』中島敦
- 『スローターハウス5』カート・ヴォネガット・ジュニア
- 『るつぼ』アーサー・ミラー
- 『スペードの女王・ベールキン物語』プーシキン
- 『灯台へ』ヴァージニア・ウルフ
- 『黄金の壺/マドモワゼル・ド・スキュデリ』ホフマン
- 『遠い声 遠い部屋』トルーマン・カポーティ
- 『知と愛』ヘルマン・ヘッセ
- 『アラバマ物語』ハーパー・リー
- 『樽』F・W・クロフツ
- 『たんぽぽのお酒』レイ・ブラッドベリ
- 『料理人』ハリー・クレッシング
- 『ワインズバーグ・オハイオ』シャーウッド・アンダソン
- 『響きと怒り』ウィリアム・フォークナー
- 『人間ぎらい』モリエール
- 『城』カフカ
- 『郵便配達は二度ベルを鳴らす』ジェームズ・M・ケイン
- 『ゴドーを待ちながら』サミュエル・ベケット
- 『幸福論』アラン
- 『肉体の悪魔』ラディゲ
- 『オー・ヘンリー傑作選』オー・ヘンリー
- 『欲望という名の電車』テネシー・ウィリアムズ
- 『チップス先生、さようなら』ジェイムズ・ヒルトン
- 『蜘蛛女のキス』マヌエル・プイグ
- 『世界の中心で愛を叫んだけもの』ハーラン・エリスン
- 『人形の家』ルーマー・ゴッデン
- 『ペスト』カミュ
- 『夜と霧』ヴィクトール・E・フランクル
- 『長距離走者の孤独』アラン・シリトー
- 『子規句集』正岡子規
- 『クレーヴの奥方』ラファイエット夫人
- 『ドリアン・グレイの肖像』オスカー・ワイルド
- 『一九八四年』ジョージ・オーウェル
- 『椿姫』デュマ・フィス
- 『マルテの手記』リルケ
- 『ボヴァリー夫人』フローベール
- 『リア王』『マクベス』ウィリアム・シェイクスピア
- 『赤と黒』スタンダール
- 『君主論』マキアヴェリ
- 『自由論』ミル
- 『マンスフィールド短編集』マンスフィールド
- 『日々の泡』ボリス・ヴィアン
- 『マルタの鷹』ダシール・ハメット
- 『クリスマス・キャロル』チャールズ・ディケンズ
- 『幼年期の終わり』アーサー・C・クラーク
- 『風にのってきたメアリー・ポピンズ』P・L・トラヴァース
- 『緋文字』ナサニエル・ホーソーン
- 『孫子』
- 『宝島』ロバート・L・スティーヴンソン
- 『ジキルとハイド』ロバート・L・スティーヴンソン
- 『アッシャー家の崩壊/黄金虫』ポー
- 『ハイ・ライズ』J・G・バラード
- 『マイ・アントニーア』ウィラ・キャザー
- 『外套・鼻』ゴーゴリ
- 『深夜プラス1』ギャビン・ライアル
- 『カヴァレリーア・ルスティカーナ 他十一篇』G・ヴェルガ
- 『完訳 チャタレイ夫人の恋人』ロレンス
- 『バベットの晩餐会』イサク・ディーネセン
- 『カンディード』ヴォルテール
- 『ずっとお城で暮らしてる』シャーリイ・ジャクスン
- 『ヘンリー・ライクロフトの私記』ギッシング
- 『九百人のお祖母さん』R・A・ラファティ
- 『サキ短編集』サキ
- 『山海経』
- 『悪魔の涎・追い求める男 他八篇』コルタサル
- 『怪談』ラフカディオ・ハーン
- 『津軽』太宰治
- 『ラ・ボエーム』アンリ・ミュルジェール
- 『鼻行類』ハラルト・シュテュンプケ
- 『金枝篇』J・G・フレイザー
- 『カラマーゾフの兄弟』ドストエフスキー
- 『荒涼館』チャールズ・ディケンズ
計92作
・・・・・・ぜーはー ぜーはー(果たして作家名を入れることまでする必要あったのか
世界文学と海外文学のちがいって?
とインタネ(ット)で検索をかけようとしたけれども
ああそうか、なんてことはない、日本も含んだすべての範囲ということだった。なんせ太宰がいる
書店本棚の前で流し見て、
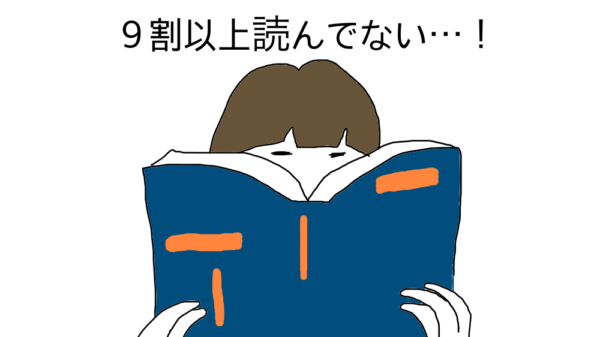
と絶句した。
その時思ったのは、
じゃあこれに掲載されている本を全部読んで、
それからこの本を読んだらおもしろそうだな だった。
で、一度本を書棚に戻した。
でも。
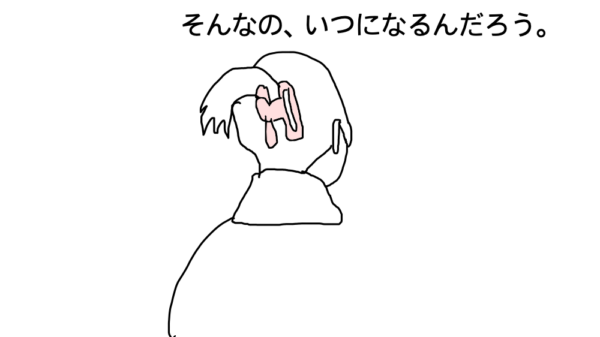
数十年後かもしれない。
いや数十年後には、この本のことを忘れてしまっているかもしれない。
いつも、大きい目標を立てすぎる。
改めて同じ本棚(たしか、詩とかのコーナーの隣)に立ち、
一番上の段に戻した本をまた抜き出し開いてみた。
読んだことのある本の項を開いてみる。
ボリス・ヴィアン『日々の泡』
仕事で、自分で選んだ本を読んでいて、ごくたまに「読み終われるかなあ」と不安に思うことがあるのだけれども、実はこの作品もそうだった。(……)あまりに合わないというか、世界観が超絶かゆいのだ。たとえば(……)「コランは敷物に調和のいい淡青色のテーブルクロスを選びだした。テーブルのまんなかにはフォルマリンの広口壜を置いたが、その中には鶏の胚子が二つ、ニジンスキー振付の『薔薇の精』を演じているように見えた。(中略)それから彼は二人のために、金の透かしを十文字に焼きこんだ白磁の皿を二枚、柄が透かし彫りになったステンレスのナイフとフォークを一揃い出してきてみたが、その柄の透かしの部分には剥製のテントウムシが……」(……)好きな人は好きかもしれないけれども、わたしは貧乏揺すりをしながら書き写していた。
なんだろう。最高。
体の中に共感の嵐が巻き起こる。
そこから著者の思う、落とし所にまとまっていく様子は圧巻。
自分の抱えていたもやもやも、一緒にまとめて(まきとって)くれたような気がして、なんだか勝手にすっきり。
そう、1つの作品に対する書評(?感想)が本の中で3ページほどなので、1作品ならその場で読めてしまうくらいの読みやすさなのだ。
もうひとつ、『ゴドーを待ちながら』の冒頭はこう。
ゴドーはほんまに来るんか!? という書き出しで始めたいものなのだが、ゴドーが来ないのは、わたしも知っていたので
わりと有名な話だと思う。なら君ゴドーが来ないんならいったい何を読まされるっていうんだよ、というのが、この作品を
未読でいる人(演劇を見ていない人)の意見かと思われるのだが、べつにゴドーが来ようと来なかろうと、読み手にはおそらく損も徳もない。
あ~(最高)
もしこの本が気になる方は、まずはぜひ最初の『華麗なるギャツビー』の書き出しも見てみてください。
そこにも言いたい(私が伝えたい良さ)エキスが凝縮されています。
これはまだ最後まで読んでないので楽しみにとっている。
そのまま抱きしめた本をレジに持って行き、
来た道をスーパーに寄りつつ家に戻り、夜が来て、部屋で
もうひとつ、読んだことのある(本屋店主との話* に出た)カフカの『城』のページをおそるおそる開いてみた。
タイトル:仕事がまったく進まない
本文冒頭:仕事が進まない。
あーよかった!
と思う。
やはりあのカフカの『城』から感じたのは、そういうことだったのかと
またも勝手に独りごちる。(すごく端的に表してくれた、ありがとう)
あーよかった だらけの本
さて、これを購入したことで、
わたしは世界文学を読むのかいなか
でも片手に新しい(未読の)世界文学、もう片手にこの本があれば、最高の最高に幸せの形だと思いませんか
本書に収録されている連載は、そもそも、『華麗なるギャツビー』って言われてもギャツビーて誰?
「なにも考えていないことの複雑さ」:『郵便配達は二度ベルを鳴らす』より
『ねじの回転』は家具の組み立ての話? みたいな疑問を解消する、という目的のもとに始まった(……)
と書かれているので、
なるほどだから読みやすいのかと納得しつつも、読みやすさの理由はそれだけじゃないだろう。
(後記)
それこそ2021年くらいから、あまり本を読まなくなった。
だから津村記久子さんの本を手にするのも久しぶりだった。
その文章を見たとき、実際のふるさとでは感じられない、
ふるさとに帰ってきたような安心感をおぼえた。
本ってすごいなあ
2025年3月30日
*本屋店主との話:東京で行った本屋。この文章より先にアップしようと思っていたけど、こっちを先に上げることにしちゃったので。近日公開!
それにしても100%オレンジさんが装画を手がけたものって外れなしなのでは
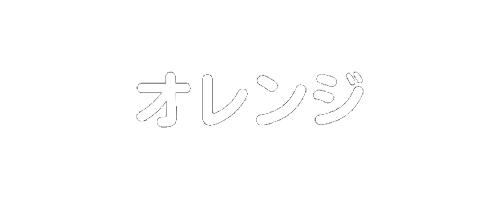
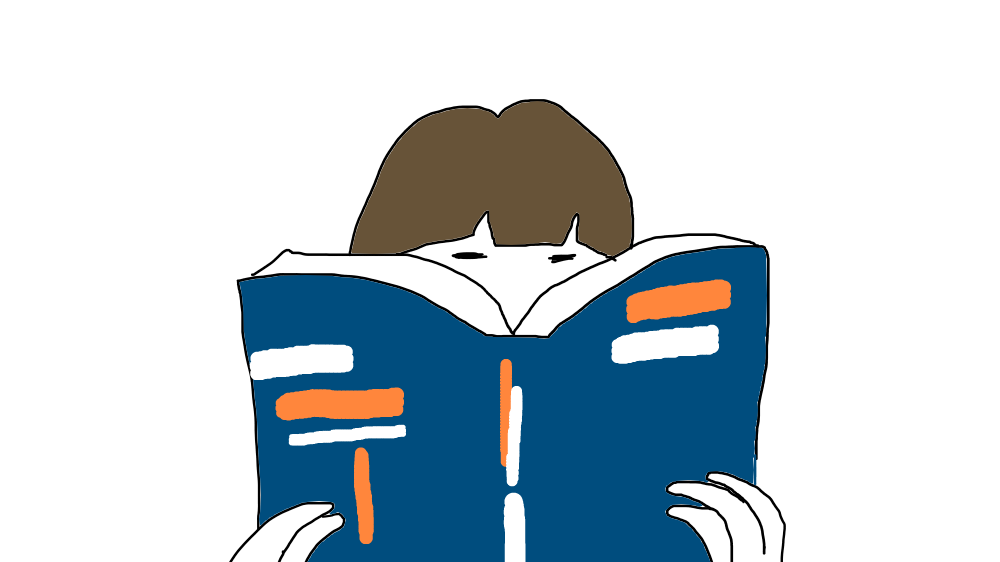






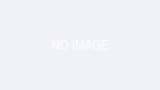
COMMENT