現代に生きる作家、今は取り壊された大仏ホテル、
そこを訪れていたかもしれない過去の作家、そこにいたかもしれない二人の女、と幽霊。
ひと月も経たないくらい前に、同じ作家の本を読んでいるんだから
2冊目の今回はまさか書かないだろうと思っていたのに書いている自分がいる。
今はない(あるいはなかったかもしれない)場所を中心に、
たくさんのストーリー、背景が立ち上がる。
カン・ファギルの長編2作目となるこの
『大仏ホテルの幽霊』は、
前作の『別の人』が女性にまつわる叙事を中心に書かれたものであるのに対し
幽霊! 女性と性暴力にまつわる話から、幽霊!!
すごい。
『別の人』は、わりといくつかの章に分けられ、(主体もその章ごとに違っ)ていたが、
今作は大きく3部+αで構成されている。
圧倒的な筆力。
前回は、翻訳がすばらしかったと書いたが、今回は、翻訳者が介在していることさえ感じなかった。
そしてとくに長編の前作と今作では、同じ人が書いたとは思えないくらいの
リズムとタッチ(というのか)に違いを私は感じた。
こんなに感じたことないくらい感じた。
この本を読んで私が思ったのは、
とどのつまり、何を真実ととるか、
自分次第なんだろうなということ。
こと幽霊の存在が漂う本作において、
私は最終3部のところが何より真実らしく感じた。
どんな小説を読んでいても、どこか暗黙の了解的に
これはフィクション、絶対的にストーリーなんだと前提している自分がいるけど、
この人の本を読んでいると、どうしてもすべてが現実のことのように思えてくる。
誰かを傷つけたい気持ちって、どうしてそんなに共感しやすいんだろう。
そう。話を信じたっていうよりは理解したってほうが、より正確な言い方な気がする。
それがどうしてかは専門家ではないからわからない。
うごめく人物の感情の描写が巧みだからかもしれないし、
時代や場所の背景について裏付けのある情報なども関係しているかもしれない。
こんなことを考えます。私はなぜ物語を書くのだろう。物語というものを、わざわざなぜ書きたがるのだろう。誰かに聞いてほしいから? なぜ? よくわかりません。不可能だと、わかっているからじゃないでしょうか? つまり、理解される、ということがです。(中略)だから身近な人に執着するのではないですか? 自分の心をわかってもらえそうな、実体のある人ですから。その実体を、ずっと感じていたいですから。 (第二部 作中に登場する作家が言う言葉)
この小説にも出てくる短編「ニコラ幼稚園」は短編集『大丈夫な人』に収録。
読んでみると、なんとも言えないざらっとした後味が、今村夏子好きな人は好きかもしれないと思った。
ひとつの動詞・行動が、実は別の意味だったのかもしれないと思わせる読後感
2025年3月11日
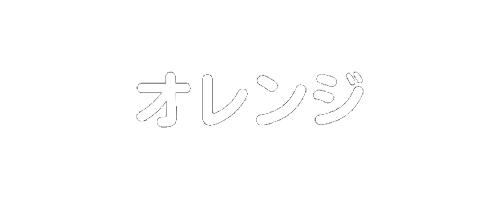
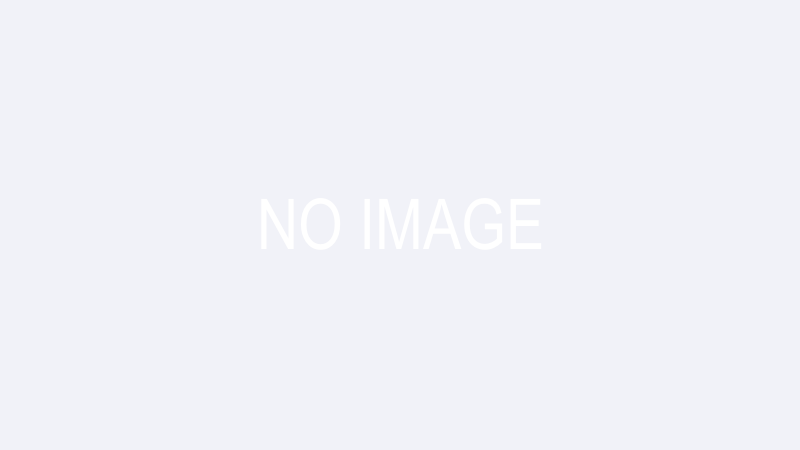


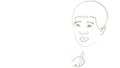

COMMENT